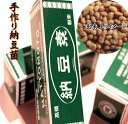ミヤギシロメの自家製納豆
先日、実家の母親から「大豆を送る」旨の連絡がありました。
いきなり何!?
よくよく話を聞いてみると、味噌作りに使用する大豆を畑で作って、たくさん収穫できた→おすそ分けしてくれるとのことでした。
ここ最近、味噌を手作りするのにハマった様子の母は、完成品を送ってくれることもしばしば。
いつの間に大豆の栽培まで始めたのだろう?と気になる点は多々ありますが、田舎ゆえに土地だけはあるので活用している模様。
聞けば、父親がやっつけ仕事で栽培した大豆で、農薬の散布は1回。
それゆえに虫食いもあるかとは思うが多めにみてくれ、と。

こちら、実家から届いた「ミヤギシロメ」という品種の大豆。(10kgも送ってきた。)
見た目にこだわるわけではありませんが、なるほど確かに黒い部分がない不思議な見た目をした大豆です。
ミヤギシロメって、どこかで聞いたことある!と思ったら、お豆腐マイスターの方が紹介していたお豆腐に使われている大豆でした。
ミヤギシロメは、わが故郷・宮城県発祥の大豆。
その特徴は、大粒で白色。
通常なら黒い「目」の部分が白いため、加工品にしたときに美しく仕上がるのだそう。
漢字にすると「宮城白目」なのかな?
味噌も豆腐も、自家製となると私にはハードルが高いので、納豆を作ることにしました。
自家製の納豆は、納豆菌とヨーグルトメーカーがあれば簡単に手作りすることが出来ます。
使用したヨーグルトメーカーのレビュー記事です。
自家製納豆の作り方 ヨーグルトメーカー使用 圧力鍋なし
ヨーグルトメーカーを使用すると、温度管理が簡単です。
湯煎したりカイロを使用したりして納豆を手作りする方法もあるようなのですが…腐敗と発酵は紙一重(らしい)ので、ヨーグルトメーカーの購入を決意しました。
納豆作りに圧力鍋を使用される方もいるそうですが、こわくて使えない私。
今回は圧力鍋の出番なしです。
自家製納豆に必要な材料は、乾燥大豆(今回は300g)と納豆菌少々。
作り方の流れとしては、大豆を浸す→ゆでる→納豆菌を付着→発酵→熟成、という感じです。
では、詳しい作り方を。
大豆をこすり合わせるようにしながらよく洗い、たっぷりの水に12時間程度浸します。


水をかえ、豆が柔らかくなるまでゆでます。3~4時間ほどを要します。
※圧力鍋でも可。
この間に、使用する道具(かき混ぜるスプーン、発酵させる容器)の消毒を。
熱湯消毒、もしくはパストリーゼ等でアルコール消毒を行います。


発酵させる容器にごくわずかの納豆菌を入れ、湯冷ましした少量の水(10ccくらい)で溶いておきます。
そこへ、湯切りした大豆を熱いうちに加えてスプーンでよく混ぜます。
豆全体に納豆菌を付着させるような感じです。


容器が取り出しやすいように(発酵時、ハンドル部分を使用しないために取り出しにくい)、ビニール袋に入れてからヨーグルトメーカーにセットします。
ヨーグルトメーカーは45度・24時間に設定し、発酵させます。
蓋はせず、ほこりよけのキッチンペーパーをかぶせる程度にしてください。
納豆の完成には酸素が必要で、蓋をしてしまうと納豆にならないのだそう。


右の写真が、24時間発酵させて完成したミヤギシロメの納豆。確かに、大豆特有の黒い部分がないです。
ここで完成としてもいいのですが、冷蔵庫でさらに24時間熟成させると旨味が増します。
完成した納豆の賞費期限は一週間とされていますが、あわてて食べるのもストレスなので、小分けにして冷凍保存が便利。冷凍保存すれば、一か月ほどもちます。


一度に使う量がごく少量なので、3g入りなのになかなか減らない粉末納豆菌。
味の感想
ひきわりだったり小粒だったり、色々な納豆がありますが、大粒の納豆ってあまり売っていないように感じます。
ミヤギシロメで作った納豆は、ほんのりとした甘みが感じられます。
大粒なので、食べごたえ十分。
美味しい納豆が出来て良かった◎
注意点としては、納豆にすると、ゆであがった状態の大豆よりもかたく仕上がるため、柔らかめに火を通すようにするといいです。
雑菌が繁殖するのを防ぐためにも、消毒をしっかり行うこと。
大豆が熱いうちに菌をまぶすのもコツです。
24時間、容器に蓋をしないまま発酵させますので、もう慣れましたが独特のにおいが漂います。